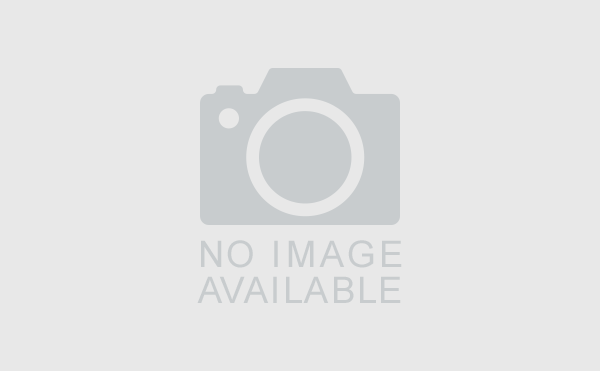「遺産分割協議の進め方」と題する講演を行いました(弁護士会姫路支部主催)
平田元秀弁護士が、兵庫県弁護士会姫路支部主催の「2025年度市民法律講座」の一環として、さる7月12日、「遺産分割~遺産分割協議の進め方~」と題する講演を行いました。その概要を紹介します。なお、以下の内容については、当WEBサイトの「市民の法律相談室」ページの「相続・遺言」欄も参考となりますので、必要に応じ、併せてご覧下さい。
お話の構成
第1 遺産分割協議の大きな流れ
第2 法定相続人の調査
第3 相続財産の調査
第4 遺産分割案の策定
第5 遺産分割協議書の作
第6 遺産分割の執行
第7 弁護士費用
<設例>
|
令和7年3月1日、父Aが死亡しました。私は父の長男です。亡父の家族構成としては、母B、長男C、長女Dがいます。母と私は実家で父と同居してきました。 |
第1 遺産分割協議の大きな流れ
1 はじめに
設例は、遺言書がないケースでの遺産分割が問題となっています。
こうした場合、遺産分割手続を進めるには、大きなお膳立てとして、次の2つの調査・準備が必要です。
➀ 被相続人の法定相続人の調査
➁ 被相続人の相続財産の調査
2 法定相続人の調査
まず、Cさんは、「父Aには妻Bがいて、子どもはCとD2人だけだ」と言われますが、不動産の名義を変えたり、預貯金を解約したり、有価証券の名義を変えたりためには、そのことを、法務局や、銀行・証券会社などに向けて証明する戸籍等資料が必要になります。
CとDの体験的事実としては子どもは2人だけだとしても、Aには離婚した前妻との間に子がいる可能性もあります。
これが法定相続人の調査です。
この調査に伴って、法定相続分が一応算出されます。
ただし、法定相続人の中に相続放棄をした者がでれば、これに伴って、法定相続分も変動します。
3 相続財産の調査
次に、遺産分割の対象となる財産を特定し、その評価額を明確にする必要があります。
Aが死亡した当時にあった財産のほか、生前贈与された財産があれば、これを持ち戻して計算する必要があります。
以下具体的に見てみましょう。
第2 法定相続人の調査
1 被相続人の終生戸籍(生涯戸籍)の取寄せ等
被相続人Aの法定相続人を調査するには、市役所(町役場)で被相続人Aの出生から死亡までの間の戸籍(「終生戸籍」「生涯戸籍」などと言います。)を取り寄せる必要があります。
妻Bは、Aの最後の戸籍(除籍)に載っています。
終生戸籍を見ると、Aに子が過去に何人いたのかが分かります。子にはCもDもいることでしょう。他に出てくるかもしれません。
子が結婚や養子縁組等に伴って別の戸籍に移っている場合、その子の転籍後の戸籍の変遷を現戸籍(最新の戸籍)まで確認・収集する必要があります。
子が死亡している時は、代襲相続が発生しますので、その子の終生戸籍を調査し、その子の子(孫)がいないかを調査し、孫がいる場合は、その孫の戸籍の変遷を、現戸籍まで確認・収集する必要があります。
このような調査により、法定相続人が、一応、確定します。
2 被相続人の最後の住所、法定相続人の住所の調査
相続の諸手続では、通常、被相続人、法定相続人を特定するために、➀氏名、➁生年月日、③住所の3点が求められます。
上記1の戸籍調査では、被相続人、法定相続人の➀氏名と➁生年月日は証明できますが、③住所は証明できません。そこで、上記1の調査に合わせて、被相続人の死亡後の住民票(住民票の除票)、法定相続人の現戸籍の戸籍附票または住民票を取り寄せることになります。
3 相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成
相続関係説明図が完成すると、弁護士は、しばしば、これを法務局の求める形に補正して、法務局に提出し、「法定相続情報」として、法務局に認証してもらいます。
この制度は、8年前の2017年5月から始まった制度です。
登記官は、戸籍関係書類一式の内容を確認し、法定相続情報の認証文付きの写しを無料で求める部数交付してくれます。
「法定相続情報」があれば、不動産の相続登記や、銀行口座の解約などの種々の相続手続の際に、相続人や代理人が、戸籍謄本の束を何度も提出する手間を省くことができます。
4 法定相続分の調査
(1)法定相続分
法定相続人の調査が終わると、各法定相続人の法定相続分が算出されます。
ただし、法定相続人の中に相続放棄をした方があれば、その方はその相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされますので(民法939条)、相続人の数も変わり、法定相続分も変動します。
(2)法定相続分の算定ルール
法定相続分の算定に関するルールをおさらいすると、次のとおりです。
➀ 配偶者は常に相続人となる(民法890条)。
➁ 配偶者以外の法定相続人は、
ⅰ 被相続人の子、
ⅱ 被相続人の直系尊属(父母、祖父母等)
ⅲ 被相続人の兄弟姉妹
であり、一番高い順位の者のみが相続人となる(民法887条、889条)。
③ 被相続人の子が被相続人よりも先に亡くなっている場合で、子や孫がいる場合には、
ⅰ子、ⅱ孫の順で代襲相続・再代襲相続する(民法887条)。
➃ 被相続人の兄弟姉妹が被相続人よりも先になくなっている場合で、子(被相続人の甥、姪)がいる場合には、
被相続人の甥や姪が代襲相続する(再代襲相続はない)(民法889条)。
⑤ 配偶者のほかに法定相続人がいる場合、配偶者とその他の法定相続人の法定相続割合は、次の通りとなる(民法900条)。
・配偶者と子 1/2:1/2
・配偶者と直系尊属 2/3:1/3
・配偶者と兄弟姉妹 3/4:1/4(父母の一方が異なる場合を除く)
⑥ 配偶者以外の法定相続人が複数いる場合、民法900条で決められている割合(⑤参照)をさらに人数で割った割合となる。
ただし半血の兄弟(父母の一方のみを同じくする兄弟)は、両血の兄弟の相続分の2分の1となる(民法900条4項)。
(3)設例の場合
<設例>の場合、相続人調査の結果が相談者の述べたとおりであった場合には、母Bの法定相続分は2分の1、長男Cと長女Dの法定相続分はそれぞれ4分の1となります。
第3 相続財産の調査
1 はじめに-相続財産、みなし相続財産、一応の相続分、具体的相続分-
相続財産調査の必要性
裁判所での遺産分割協議(調停)は、各相続人の「具体的相続分」を基準・目安・指標として行われます。
この「具体的相続分」は、被相続人が相続開始時(死亡当時)有していた財産(相続財産)の価額を基本とし、これに、生前贈与(特別受益)がある場合は、その贈与の額を加え(民法903条1項)、寄与分がある場合は、その寄与分を控除して、「みなし相続財産」の額を算定し(民法904条の2)、この「みなし相続財産」に、各相続人の法定相続分を乗じて得られる「一応の相続分」から、生前贈与(特別受益)を受けた者についてはその額を控除し、寄与分がある者についてはその額を加えて、算定されます。
そうしますと、何をするにせよ、被相続人が相続開始時(死亡当時)有していた財産(相続財産)と、その評価額を整理しておくことが、まずは必要ということになります。
遺産分割のための相続財産調査と相続税の申告のための相続財産調査
なお、相続財産の価額が相続税の基礎控除額を超えるときは、相続税の申告が必要になります。
設例の場合、相続税の基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)は、4800万円となります。
そこで、相続財産の価額についてみますと、不動産の価額は、評価証明額をもとに2000万円となっていますが、相続税評価額だと、これを少し超えてくると考えられます。積極財産は5000万円を少し超えるでしょう。
他方、相続税の算定では、一定の葬式費用を控除することができます。本件では150万円という設定です。相続債務がいくらあるのか、微妙ですが、本件では相続税がかかる可能性があります。
この場合、税理士に申告を依頼するときには、税理士の相続税申告書の「第2表」、「第11表」(付表を含む)及び「第13表」での調査項目と、遺産分割のための相続財産の調査項目は多くの場合、重なってきます。そこで、税理士と連携して作業を進めること、弁護士を依頼されるときには、依頼される税理士と連携して作業を進めてもらうことも、有益です。
2 相続財産目録(遺産目録)の調整
⑴ 相続財産として考えられる項目
相続財産として考えられる項目には次のものが挙げられます。
Ⅰ 積極財産
A 不動産(土地・建物)
B 預貯金・現金
C 保険・共済
D 有価証券(金融商品)
E 車両
F その他の財産
Ⅱ 消極財産(相続債務等)
G 相続債務
H 葬儀費用・法要代
以下、それぞれについて、少し詳しくお話しします。
Ⅰ 積極財産について
A 不動産(土地・建物)について
被相続人宅には、市役所(町役場)から、「固定資産税・都市計画税 納税通知書」が届いているはずです。まずはこれを手がかりに、土地については所在・地番・地目・地積及び固定資産評価額を、建物については、所在・家屋番号・種類・構造・床面積及び固定資産評価額を把握しましょう。
その後、関係市役所(町役場)から被相続人名義で固定資産課税台帳(名寄帳)を取り寄せ、非課税の不動産についても把握します。
なお、来年2026年2月2日から「所有不動産記録証明制度」が始まります。法務局で、被相続人名義の不動産の一覧リストにして、証明書にしてくれます。そこで、2026年2月2日以降は、この証明書で、不動産を把握することになります(不動産登記法119条の2)。
土地の評価額については、相続税評価額(路線価・倍率)も把握します(国税庁の財産評価基準書の路線価図・評価倍率表を活用します)。
地価公示価格(国土交通省Webサイト「不動産情報ライブラリ」)で評価を試みる場合もあります。
上記で把握した不動産について、法務局で登記事項証明書(土地・建物)を取り寄せ、これをもとに、上記各項目を見やすく整理した不動産の目録を作成します。
各不動産の現在の用途、管理者、使用者等の情報を、分かる範囲で備考欄に書き込みます。
B 預貯金・現金
- 預貯金については、被相続人の通帳の記録(紙媒体)ないしスマホ等のデジタル媒体の取引履歴(出入金記録)を把握します。デジタル記録は紙印刷またはダウンロードをしておく必要があります。
取引履歴は、相続開始日(被相続人の死亡日)及びそこから遡って少なくとも1年間分*、及び相続開始日から調査日現在までの分を把握します。
* 口座の動きから、使途不明の、何者かの財産の不法領得等を疑わせる「疑わしい出金」が認められるとき等には、その必要に応じさらに遡って調査します。 - 預貯金については、金融機関の窓口で、「法定相続情報」を提出すれば、相続人なら単独でも窓口で照会し、回答をうけとることができます。
相続開始日の残高は、残高証明書の交付を受けることになります。
弁護士は、これらの情報を弁護士会照会手続で取り寄せることができます(ただし、有料です。弁護士会の手数料と、弁護士の事務手数料を併せて、1通(1回)1万円程度を要します。)。 - 現金について
例えば、被相続人の通帳から、被相続人のキーパーソンをしていた相続人が、被相続人の債務の支払に充てる等のため、まとまって資金を引き出し、預かっている場合があります。こうしたものは、相続人の「預り金」の性質を持ちますが、遺産の性質としては「現金」として計上しています。この場合、備考欄で「相続人○○の預り金」等と記載します。
C 保険・共済
- 死亡保険金は、被相続人が契約者・被保険者で、受取人欄に特定の相続人の名前が書かれている場合、受取人に指名された者は、相続ではなく、固有の権利として保険金請求権を取得するので、その特定の者が受け取った生命保険金は、遺産分割の対象とはなりません(最判昭和40年2月2日)。
ただし、特定の相続人のみがその保険金を受け取ることの不公平が著しいものであるという特段の事情があるときは、民法903条を類推適用して特別受益と認められる場合があります(最判平成16年10月29日)。
この場合、保険金のうち、被相続人が負担した保険料が全保険料額に対して占める割合に相当する額が、特別受益であると認める説が、通説です。
なお、上記の最高裁判決の考え方とは別に、一般的に、被相続人が支払った保険料額は特別受益となる、との見解もあります。 - 1.と異なり、死亡保険金で、受取人欄に特定の相続人の名前が書かれておらず、受取人が「法定相続人」と書かれている場合には、当該保険金は、相続財産となります。
- 満期保険金(被保険者が契約時に設定した満期日まで生存していた場合に支払われる保険金)は、死亡時にまだ被相続人が受け取っていない場合で、受取人が被相続人の場合には、法定相続人がこれを相続します。
この保険金については、遺産分割の対象となるとの見解と、可分債権として相続分に応じて相続されるとの見解とがあります。 - 共済では、農協の建物更生共済などが、相続財産としてよく計上されます。
D 有価証券
証券会社の口座で管理する上場有価証券等、信用金庫等の出資証券、暗号資産交換業者の口座で管理する暗号資産、同族会社の非上場株式などが挙げられます。
上場有価証券等については、少なくとも、相続開始日及び調査日現在の分について、口座の証券会社から取引所、銘柄、数量、評価額を証明する資料を取り寄せます。
暗号資産についても、口座の暗号資産交換業者から、同様の資料を取り寄せます。
同族会社の非上場株式については、会社から決算書を取り寄せます。
E 車両
自動車については、登録事項情報(車検証の写し)を入手するとともに、レッドブックやネット上のオークション価格等で相続開始日及び調査日現在の評価を把握します。
F その他積極財産
貴金属、着物、絵画、刀剣類、書画、扇子、皿、壺、家財道具、事業用財産等が考えられますが、実務上は、相続税申告書第11表の付表4に計上のある動産について、その評価額で整理することが多いと考えられます。ここに載っていないものは、争いとなれば、存否、内容、数量、評価額等の認定が難しい場合が多いと考えられます。
Ⅱ 消極財産(相続債務等)について
G 相続債務
- 相続債務としては、通常、家賃、水道光熱費、病院代、税金(固定資産税、市県民税、社会保険料等)が、挙げられます。
金銭債務は、本来は、可分債権として、法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じて、これを承継するものです(最判2小昭和34年6月19日)。そこで本来遺産分割の対象財産とならないのですが、相続人の1人が立替払いをしたりしていることが多いので、実務上は、遺産目録に掲げ、積極財産から消極財産を控除したものを相続財産として、調整の対象とすることが多いといえます。 - 相続債務として、住宅ローンその他の銀行ローンが残っていることがあります。ローンについては、相続人の1人が「引き受ける」、「責任を持って支払う」ものと相続人間で合意しても、それを金融機関の側が承諾しないと、結局は相続分に応じて分割承継されますので、そのことに注意する必要があります。
H 葬儀費用・法要代
葬儀費用(通夜・告別式、火葬等の過程で要する費用)、香典、法要代(四十九日、百箇日の法要代、位牌代、納骨代、永代供養料、墓仕舞い費用、墓建立費用等)は、相続開始後に生じた債務であり、一時的には祭祀主宰者、祭祀承継者が負担することとなり、相続財産に関する費用ともいえないので、その分担について争いがあって、調停で調整が図れない場合には、民事訴訟手続で解決されることとなるとされています。
ただし、実務上は、葬儀費用(常識的範囲内のもの)から香典の半金(香典返し分)を控除した額を消極財産等の1つとして相続財産目録に計上し、遺産分割協議の俎上に載せることは、よく行われています。
3 特別受益、寄与分について
(1)「みなし相続財産」
特定の相続人に、特別受益(本件事例では、生前贈与)がある場合は、上記2の「相続財産目録」で調製した相続財産に加え、また、特定の相続人に寄与分がある場合は、相続財産からこれを控除して、「みなし相続財産」目録を作ります。
ただし、相続開始から10年以上経過したのに、まだ遺産分割協議が成立していない場合には、原則として、特別受益の持ち戻しや寄与分の控除を権利として主張することはできなくなるので(民法904条の3)、注意してください。
(2)生前贈与について
ア 概要
特定の相続人に、特別受益がある場合に、その額を相続財産に加えることを「特別受益の持ち戻し」と言います。
特別受益には、遺言で財産を相続人に譲渡する「遺贈」と、「生前贈与」の2種類がありますが、本件の設例では、遺言書はないので、生前贈与が問題となります。
イ 要件
生前贈与とは、「相続財産の前渡しとみられる」贈与のことを言います。
結婚持参金、養子縁組贈与金などは、金額が多額の場合には、生前贈与となります。結納金・挙式費用の贈与は特別受益にはならないとみられています。
私立の医科・薬科等の大学の入学金・授業料のように特別に多額の教育費は生前贈与にあたるものと見られていますが、そうではない大学学費は生前贈与に当たらない(遺産の先渡しの趣旨を含まない)と見られています。居住用不動産の贈与やその取得のための金銭の贈与等は、生計の基礎として役立つ財産上の給付であり、生前贈与とみられています。
ウ 設例について
長女は、20年前に自宅を建てるときに500万円を父から出してもらっています。
また8年前に長女の夫の飲食店の開業資金として200万円を父から出してもらっています。
上例の500万円、200万円はいずれも生前贈与とみられます。合計は700万円です。
なお、生前贈与は、「遺留分」の基礎となる財産の算定の際には、相続開始前10年以内のものに限られますが、「遺産分割」の基礎となる財産の算定の際には、こうした限定はありませんので、20年前の生前贈与も、「みなし相続財産」として持ち戻しを行うべきことになります。
(3)寄与分について
ア 概要
特定の相続人に、被相続人の事業に関する労務の提供、または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、その額を、相続財産の価額から控除して、「みなし相続財産」目録を作ります。特別の寄与をした相続人は、「みなし相続財産」に法定相続分を乗じて得られる額に、寄与分の額を加えたものを相続することになります。(民法904条の2)
イ 手続・要件
ただし、寄与分を家庭裁判所の調停・審判で主張するためには、特定の相続人によるその旨の申立が必要です。また、寄与分が認められるためには、次の4つの厳しい要件があります。
① 相続人自らの寄与であること
➁ 当該寄与行為が「特別の寄与」すなわち、被相続人との身分関係に基づけば通常期待されるような程度を越える寄与であること(夫婦間協力義務、親族間の扶養義務の範囲内の行為は特別の寄与にあたらないとされています。)
③ 被相続人の遺産が維持又は増加したこと
相続人の行為によって、その行為がなかったならば生じたはずの財産の減少や債務の増加が阻止され、その行為がなかったなら生じなかったはずの被相続人の財産の増加や債務の減少がもたらされること(この要件が相当厳しいです。)
➃ 寄与行為と被相続人の遺産の維持又は増加との間に因果関係があること(精神的な援助、協力があるだけでは、寄与分は認められません。)
ウ 設例について
設例では、「父は自宅で2年間癌の闘病生活を送りましたが、私と妻が晩年その看病・介護にあたってきました。」ということで、 療養看護型の寄与が主張されています。
父の闘病生活を支えるための看病・介護が、同居の親族としての扶助義務の範囲内に収まっているものと見られるときは、寄与分は認められません。「私」の妻の看病・介護は、「私」の履行補助者とみられる範囲で、「私」の寄与と同視されます。癌の闘病生活という場合、医療機関の支援、保険金給付、訪問看護、訪問介護等の支援も受けている可能性があり、こうした中で、寄与分が認められるためには、無償で、継続的に、訪問看護や訪問介護の支援が受けられないためにこれに代替するような形で、そうした看護・介護を行ってきたというような事実関係の主張立証が必要となると考えられます。また認められたとしても、金額的には介護・看護報酬程度となります。
事実上、多くの事例では、その主張立証はハードルが高いと言えます。
なお、設例の相談者の妻の看病・介護が、夫の履行補助者という位置づけではなく、独立の支援であるという場合もあります。この場合は、特別寄与料(民法1050条)として相続人にこれを請求することができる制度が設けられていますが、寄与分同様、要件は厳しいです。また、相続開始のときから最長で1年を経過すると、この請求権は消滅します。
4 具体的相続分の算定
⑴ 概要
各相続人の「具体的相続分」は、「相続財産」の価額に、遺贈・生前贈与(特別受益)がある場合は、その額を加え、寄与分が認められる時は、これを控除して、「みなし相続財産」の額を算定し、この「みなし相続財産」に、各相続人の法定相続分を乗じて得られる「一応の相続分」から、遺贈・生前贈与を受けた者は、その遺贈額・生前贈与額を控除して算定し、寄与分がある者については、その寄与分の額を加えて算定します。
⑵ 設例について
令和7年3月1日死亡・遺言書なし
父A (被相続人)母B 長男C 長女D
○ 自宅土地建物 2000万円(評価額
○ 預貯金 2000万円
○ 有価証券 1000万円
合計 5000万円
★ 葬儀費用 150万円(長男Cが負担)
★ 長女D:20年前 500万円出してもらう(住宅資金)
:8年前 200万円出してもらう(夫の飲食店開業資金)
★ 長男C:妻とともに2年間看病・介護にあたってきた。
上記設例で、母B、長男C、長女Dの具体的相続分を考えてみましょう。
相続財産は、5000万円(土地建物の評価を固定資産評価額でみると合意したと仮定します。)
葬儀費用150万円は、相続財産から控除する(控除した分はCにつける)と合意したと仮定します。)
この場合、「相続財産」の額は、4850万円となります。
長男Cは寄与分主張を諦めたと仮定します。
この場合、「みなし相続財産」の額は、4850万円+700万円=5550万円となります。
そうしますと、
・ 母Bの具体的相続分:5550÷2 =2775万円
・ 長男Cの具体的相続分:5550÷4+150(葬儀費用) =1537万5千円
・ 長女Dの具体的相続分:5550÷4-700(特別受益) = 687万5千円
合計 5000万円
こうして、具体的相続分が決まると、いよいよ、遺産分割案の策定です。
第4 遺産分割案の策定と協議
設例では長男Cと同居する、高齢と考えられる母Bが存命ですので、例えば、次のような案が考えられます。
母 B:自宅土地建物を取得する 2000万円
預貯金・有価証券を換金し、母B775万円、長男C1537.5万円、長女D687.5万円に割り振って分ける。
あとは協議です。できるだけ喧嘩とならないように、情理を尽くしましょう。
第5 遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書作成のポイントは次のとおりです。
- 何に使うのか、どこに出すのか、を明確に意識すること
- だれが預貯金・有価証券を換金するのかを明確に意識すること
- 不動産の相続登記手続に支障のない協議書とすること(司法書士との連携)
- 共同相続人が多い場合
遺産分割協議書には、連名方式と、単名方式があること - 相続税納付時期との関係
相続開始後10ヶ月納税期限が来ること、その前に遺産分割協議を成立させなければならないということはないこと、ただし、納税期限には誰かが納税しなければならないので、あとで、過分に相続税を納めた相続人との間で調整が必要となってくること。
第6 遺産分割の執行
遺産分割の執行としては、次に箇条書きしたような事項が考えられます。
- 不動産の相続登記
- 未登記家屋の市町村での所有者変更届
- 預貯金の解約
- 有価証券、暗号資産の換金
- 相続人への振込
(なお、本レジュメの著作権は弊所に留保されておりますので、無断複写複製はご遠慮下さい。)