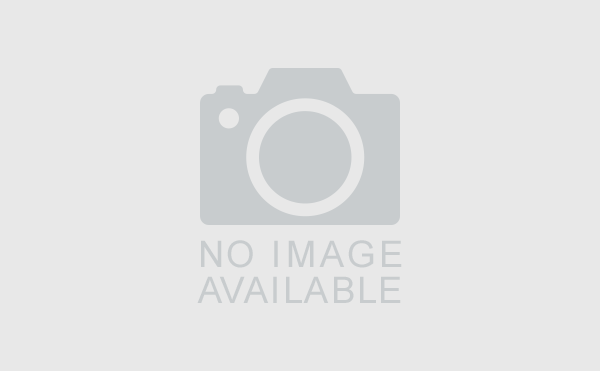水回りぼったくり商法姫路訴訟で原告勝訴(神戸地裁姫路支部R7.3.19判決)
姫路判決の結論の概要
水回りぼったくり商法姫路訴訟の第一審(神戸地裁姫路支部令和4年(ワ)第40号)の判決が令和7年3月19日に言い渡され、原告ら13名全員、勝訴判決となりました。以下、本稿で「姫路判決」といいます。
原告らの提訴時の請求額と、口頭弁論終結時の請求額とは、途中、被告となっている本件商法の協力業者の中に原告らの請求を認めて被害弁済をした者がいたため、変更されており、口頭弁論終結時の原告らの請求額は、合計326万2198円となっていました。一審判決は、このうち、294万4214円の賠償を命じました(主張した損害の一部が認められなかった原告はいますが、敗訴した原告はいません)。
重要な判断のポイント(2つ)
第1 本件ぼったくり商法の取引手法による取引は不法行為を構成する
判決は、「第3 当裁判所の判断」、「2 争点1及び争点2(個別被告らの各不法行為及び対応する原告の損害)」、「(1)判断枠組み」の中で、次のように述べています【下線部は筆者】。
|
「前提事実及び上記1の認定事実を総合すると、被告和田は、被告会社の広告上では低額な「基本料金」を強調しながら、協力業者に対しては、その「基本料金」とかけ離れた高額な契約を締結するよう促し、そのためには、依頼者の意向と実情に反する工事をやらなくては仕方がないと依頼者に思わせて高額な代金額の契約に応じさせる手法などを指導・助言した上、契約単価を上げることのできない協力業者との業務提携を解消したり罰金を支払わせたりしていたものである。 |
上記の下線部の「本件手法」は、姫路弁護団が、「本件ぼったくり商法」と定義して繰り返し主張してきた手法とも、重なりあいを認めることができます。
判決は、本件手法として、いくつかの違法となる要素(類型⑴、類型⑵は、暴利行為準則の応用として詐欺的欺まん的要素を重視するもの、類型⑶は、暴利行為準則の典型例として、対価が著しく高額である点を重視するもの、類型⑵、⑶として提示する最後のものは、暴利行為準則の主観的、及び客観的諸要素を総合的に考慮するものといえそうです。)を上げていますが、原告13名に対する各個別被告の行為のあてはめのところを見ると、いずれも、上述の本件手法に沿った行為として、社会的相当性を超える手段及び態様による違法な取引であると認定しており、その中では、本件手法の各類型を要件的に見るのではなく、「上記1の認定事実」と個別事案について認められる事実とをもとに、暴利行為準則の適用または応用と考えられる各類型に、柔軟にあてはめるかたちで、社会的相当性逸脱を認定しています。
第2 本件手法による損害については、損益相殺または損益相殺的な調整によって損害額を控除すべきではない
姫路判決は、続いて、第3の2の「(15)損害額について」の中で、次のように述べています。【下線部は筆者】
|
なお、原告らが、個別被告らから、本件各契約中の一定の修理作業については提供を受けていることや、現に修理依頼をしたトラブルを解消したことから、不法行為と同一の原因により利益を受けているものとして、損益相殺又は損益相殺的な調製によって、損害額を控除すべきかが問題となる。 |
この判断に関連する、近時の、最高裁判例としては、次の2つを上げることが出来ます。
平成20年に確立した、不法原因給付のケースにおける損益相殺不許の判例規範の考え方、「依頼者の窮地や無知につけ込んで高額な契約を締結させた」レスキュー商法による取引被害にも拡張ないし応用した点が、姫路判決のもう一つの重要な判断点です。
判例が不法原因給付事案における損益相殺的処理の不許をいう場合、その前提には、当該取引が取引上の公序(公序良俗違反-民法90条、強行法規違反-民法91条)に違反して無効であると評しうる状況があるといえるわけですが、本件判決は、明示はしていませんが、「本件手法」(弁護団のいう「本件ぼったくり商法」)による取引の場合も、同じ価値状況にあると見ているものといえます。
➀ 最判平成20年6月10日民集62巻6号1488頁
いわゆるヤミ金融業者が元利金等の名目で違法に金員を取得する手段として著しく高利の貸付けの形をとって借主に金員を交付し,借主が貸付金に相当する利益を得た場合に,借主からの不法行為に基づく損害賠償請求において同利益を損益相殺等の対象として借主の損害額から控除することは,民法708条の趣旨に反するものとして許されないとされた事例
② 最判平成20年6月24日判例時報2014号68頁
Yが投資資金名下にXから金員を騙取した場合に,Xからの不法行為に基づく損害賠償請求においてYが詐欺の手段として配当金名下にXに交付した金員の額を損益相殺等の対象としてXの損害額から控除することは,民法708条の趣旨に反するものとして許されないとされた事例
2025年3月20日 平田元秀 Produced
2025年9月17日 平田元秀 Edited