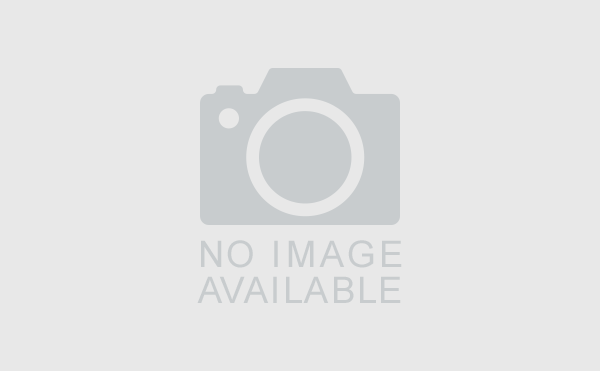民主主義の足下と「集合体としての国民」と石破さん
当番が回ってきて、今、地元自治会の副会長をしています。会議資料を作ったり、回覧物を作って回したりしながら、民主主義の足下をみつめています。
ψ ψ ψ
10月27日の衆院選では、戦後3番目に低い投票率なのに与党自民・公明が過半数割れを起こし、自公国連立のないまま(少数与党のまま)政権が続く、という稀な事態が発生しました。就任8日後に解散権を行使した石破首相は、これを「政治資金問題などをめぐり、国民の政治不信を招いた事態」と総括しました。そうなのでしょうか。
裏金問題、政治と金、権力私物化の問題でいえば、今回のパーティー収益不記載問題よりも前に、「森友加計(もりかけ)」の問題がありました。森友学園問題では、安倍首相と史観を共有し、夫妻同士が親しい関係にあった籠池理事長の学園に、大阪の国有地が、破格の値段で販売されました。しかも、責任追及の最中に、土地取引に関する公文書が財務局により改ざんされました。加計学園問題では、獣医学部の新設にあたり、文科省が「総理のご意向」の下、首相と旧知の仲にあった加計学園1校を選定・認可しました。しかし、「森友加計(もりかけ)」後の衆院選で、与党は圧勝しました(2017年)。「桜を見る会」事件では、安倍後援会の前夜祭収入不記載が発覚しましたが、その後の参院選でも与党は勝利しました(2019年)。
だから、「マスの集合体としての国民」の判断については、もう少し別の見方をした方がいいのではないかと思います。
11月5日の米大統領選挙では、大富豪で最高に自分ファーストのトランプが、階級社会の現状に不満を持つ人々の喝采を受けて政権に返り咲きました。同月17日の兵庫県知事選挙では、パワハラ疑惑の下、県議会の全会一致の不信任を受け失職した元知事が、SNSを見て元知事の演説を見に来た群衆の激励を受けて再選したりしました。そこには「価値の転倒」が起きています。考えてみると、小泉純一郎氏は、今日では極端な新自由主義を推進したと総括される政治を進めましたが、政権には力がありました。安倍晋三氏も権力私物化を批判されましたが、政権には力がありました。
これらに共通する点を考えると、そこには、①「強烈なリーダーシップ」、②「無名の国民に直接届く言葉や方法の徹底した選択」、③「ぶれない信念のある感じ」、④「無名の弱者が抱く憤りや憎悪や嫉妬や不安などの感情に訴えて、強者に立ち向かっていくようなイメージ」があると思われます。小泉さん、安倍さん、トランプさん、斎藤さんにはいくつ該当するでしょう。岸田さん、石破さん、ハリスさんは違うタイプです。
ψ ψ ψ
大衆の「ルサンチマン」に訴え、潜在的強者を敵と見立てて煽り、自陣の訴求力を創り出し、自陣の政敵を打ち倒す動き方があります。毛沢東の文化大革命もそうでした。こうしたある意味「伝統的」な手法は、日本のような年寄り国家においても、格差や貧困の拡大等の社会の深部でのマグマ上昇があるときであって、今のように、家族も会社も労働組合も政党も地域も学校も祭りも宗教もあまり強くない、個人がバラバラにスマホを見ている時代にあっては、むしろ勢いを取り戻すのだと思います。
ψ ψ ψ
民主主義の足下を見つめています。
石破さんは、いつ内閣不信任案が可決されてもおかしくない少数与党の政権、全て議論を公開して合意を形成しなければならない政治を切り盛りします。だったら、与野党、政策毎に合議をつくして、企業献金の禁止、夫婦別姓制度の導入、臨時国会の召集期限を定める国会法の改正等の、いままでできなかった良心的な立法を通したいものです。また、バラバラ化した国民の心と財産を奪われないよう、国民のサイバー領域にシビリアンコントロールを及ぼし、そこに「いわば自治会や市や国のような」民主的な公共機関を構築する大きな施策を通したいものです。
(2024年11月30日記)
本稿は「市民法律だより」2025年1月号に掲載されました。